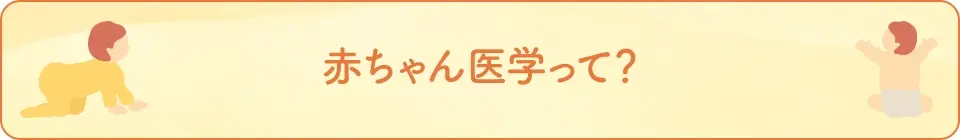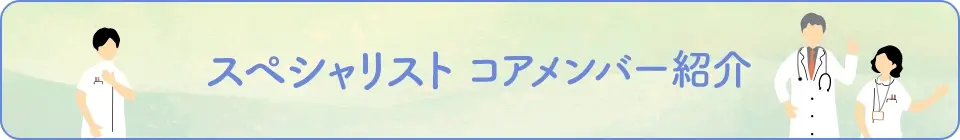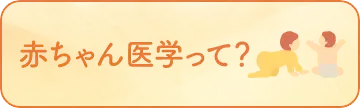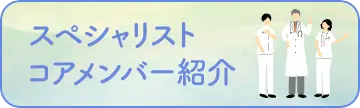添い乳(夜間授乳)
#睡眠
夜泣き対策の1つとして、赤ちゃんにおっぱいを含ませて落ち着かせる「添い乳」(夜間覚醒時の授乳)があります。
夜間授乳の背景には、「赤ちゃんが望むのであれば、与えることが愛着形成につながる」、および、「赤ちゃんは空腹のために目が覚めると泣く」という解釈があります。しかし、赤ちゃんは、生後4ヶ月頃にはすでに夜を通して眠りが持続するように成長しており、心やからだを健やかに育むためには、一晩中眠りが続くことが大事な要素となります。夜に目覚めてしまうのは、睡眠の持続が完成していないためであり、空腹のせいではないということもわかっています。
したがって、夜に目覚める度に授乳する習慣が続くと、生後2−3ヶ月まではよく寝ていてくれたのに4ヶ月過ぎから逆に夜に目覚めてしまう回数・時間が増えるという、生活リズム(体内時計)が作られてしまうことがしばしばあります。赤ちゃんへの愛情が、結果的に赤ちゃんのためにならない状態を作ることにつながってしまうのです。
夜泣きが始まり、夜中に何度も泣いて、目を覚ますと保護者も大変で、疲れが取れずゆとりのある子育てにはなりません。できれば、夜にまとまって眠れるように、生後4―6カ月以降は「添い乳」(夜間授乳)はできるだけ控えていくことをおすすめします。
夜中に赤ちゃんが目覚めたと感じた時は、極力手をかけず、赤ちゃんが自分で自分の気持ちを整えて再入眠する(self -soothing)を身につける機会を与える辛抱強さが保護者には求められます。すぐに手をかける過敏な対応はかえって赤ちゃんの感覚も過敏にしてしまい、頻繁に目覚めたり、長い時間起きていることにつながりやすくなります。それは、心身のバランス良い発達に必要な「睡眠持続性」の成長を邪魔してしまうのです。
フランスでは、新生児期を過ぎると、夜は授乳なしで朝まで一人で眠る習慣づけが行われ、夜泣きも少ないと言われています※。フランスの親が育児の常識として体内時計の知識を持ち、赤ちゃんにも「夜は眠りによる脳の成長のための時間であり食事の時間ではない」ことを実践的に教えていくという背景があるようです。関心を持たれた方は本を参考にしてみてください。因みに、アメリカでも生後3ヶ月以降の夜間授乳はやめるように勧められています。
- お話をお聞きした先生
-
 小児科医熊本大学 名誉教授三池 輝久 先生
小児科医熊本大学 名誉教授三池 輝久 先生専門は、小児神経学、小児の睡眠など。日本眠育推進協議会理事長。30年以上にわたり子どもの睡眠障害の臨床および調査・研究活動に力を注ぐ。